
2021.12.08
<対談> ヤマザキマリさん
漫画家、文筆家・ヤマザキマリさんが語る、
地球に愛される人、家族の距離感、エトセトラ…
*この対談は、2021年12月に公開されたものを再掲載しています
自由で一風変わった子ども時代を、北海道の大自然と芸術に触れながら過ごしたというヤマザキマリさん。既存の子育ての概念に囚われない、おおらかでダイナミックなお母さまとの日々、17歳でイタリアへ渡ってからの波瀾万丈のエピソードや、イタリアのご家族との愉快なご関係、ご自身のオリジナリティあふれる子育てなどを、爽やかにユーモラスに語るヤマザキさんの著書に、元気や勇気をもらった方も多いと思います。「地球に愛される人になれ」「世界はここだけじゃない」「失敗は、人間という生きもののあり方として必要不可欠」「大切なのは、同じ時空で生きているということだけでリスペクトし合えること」などなど、ヤマザキさんの語る言葉は私たちに、生きて行くうえで自分たちの前に立ちはだかる壁とどう向き合い、どう乗り越えていくかのヒントを与えてくれます。緑豊かな等々力渓谷を眼下に望むアトリエを兼ねたご自宅でお話をお伺いしました。
Photo : Yoshihiro Miyagawa
ヤマザキマリ( Mari Yamazaki )
漫画家・文筆家・東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。イタリア人比較文化研究者との結婚を機に、エジプト、シリア、ポルトガル、アメリカで暮らし、現在はイタリアと日本に拠点を置く。1997年より漫画家として活動。2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。平成27年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。平成29年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。
著書に『とらわれない生き方 母として』(KADOKAWA)、『ヴィオラ母さん』(文春新書)、『プリニウス』(とり・みき氏との共著/新潮社)、『オリンピア・キュクロス』(集英社)、『ヤマザキマリ対談集 Diálogos』(集英社)、『ムスコ物語』(幻冬舎)など多数。
趣味は、昆虫採集・飼育、南米文学と南米音楽、温泉巡り。
三枝:本日はどうぞよろしくお願いいたします。
先日、養老孟司先生と対談をさせていただいた時、資料を色々拝見していましたら、ヤマザキさんが先生と対談されている本に出会いました。その対談がとても面白くて。ぜひお会いしてみたいと、養老先生にご紹介をお願いした次第です。
ヤマザキさん(以下敬称略):そうでしたか。養老先生とは昆虫つながりなんですよ。先生のような、社会とちゃんと接点をもちながら徹底的にマニアックな部分も持ち合わせている方というのは、実はなかなかいません。だから先生に惹かれて寄っていく人が大勢いるのでしょうね。
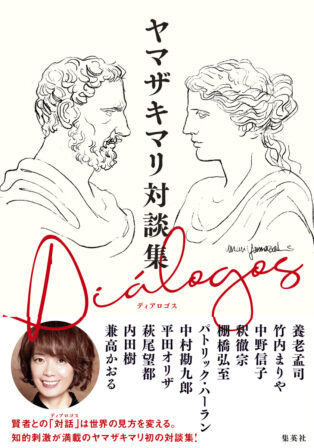
『ヤマザキマリ対談集 Diálogos』集英社
三枝:ヤマザキさんの漫画はもちろん、ご著書も拝読させていただきました。大変チャーミングな人生を歩んでいらっしゃるヤマザキさんに、我々が気づいていない視点で、今の時代子ども達にとっての善き体験のヒントをお伺いしたいと思っています。資本主義経済の限界と言われつつも、拡張・拡大を繰り返すような従来型の資本主義からなかなか離れられず、また特に都心部では子どもたちが自然から離れたコンクリートジャングルの中で育っている。そういう時代の中で、少しでも子どもたちの未来が明るくなるようなお話がお聞き出来たら嬉しいです。
ヤマザキ:チャーミング…ものは言いようですね(笑)。謂わゆる波瀾万丈な人生ってやつです。
そもそも私がなぜ昆虫好きになったかの話をしましょうか。養老先生と一緒の趣味といっても、私は標本よりも、どちらかといえば生きている虫を見ることが好き。
私の母は北海道という本人と全く縁のない土地でヴィオラ奏者として交響楽団に所属していたシングルマザーでした。頑張って働いて私たち姉妹を育ててくれましたが、他のお宅と違って、お母さんがご飯を作って待っていてくれるというような家ではなかった。ですから、寂しさとか孤独感を紛らわすために、私は家より外にいる時間が長くなったのですが、昆虫のように意思の疎通が出来ないものと一緒にいるのが楽しくなっていったんです。よく、「犬や猫ならコミュニケーションが成立するけど、虫は何を言ったって理解してくれない」と言う人がいますけど、でも、私はむしろその方が面白かった。地球上の生物として共生している、という実感が心地よかった。地球は私たち人間だけのものではない、こういう生き物たちが一生懸命生きているところなんだと感じると、すごく広い、大きな地球空間が全て自分の家のような感覚になってくるんですよ。確かに寂しかったけれど、それが私にとってはとても良い教育になったと、今では思うんですね。母の方も、北海道の大自然の中で私が活き活きとしているのを見て、これでいいんだという風にどこかで思っていたと思うんです。
三枝:なるほど。
ヤマザキ: 私は、子どもというのはどこかで孤独感を感じる機会がちょっとだけでもあった方がいいと思うんです。今の親御さんは、子どもに嫌な思いをさせたくない、失敗や屈辱を感じることのないように、孤独にさせないようにということにばかり気を使いますね。でも私は、適度な失敗や孤独感は人間の成長にとって必須要素だと思っています。ネガティブな経験だとして避けて通ってしまうと、いざという時にも誰かに依存しなければならない、一人でいるのが怖い、失敗するのが恥ずかしいから誤魔化す、そういう大人になってしまうと思うんです。
人間には悲しく寂しい感情もあるということを知るのも必要です。だから、時々、お母さんが忙しい時に子どもだけでお留守番させるとか、ひとりで買い物に行ってもらうとか、ほんのちょっとがんばって冒険させなきゃいけない時があると思っています。
子どもに、「頼れるのは自分しかいないんだ」と思わせる機会を持たせるかどうかで、将来が違ってくると思うんですよね。

三枝:おっしゃる通りで、親はどうしても子に失敗させないように先周りしてしまいがちですね。今は、世の中全体が過保護というか、そういう傾向が出ている気がしますよね。
ヤマザキ:心配なのはわかるのですが、人間の社会は危険がいっぱいであることを、人間は必ずどこかで知らされます。だから、子どものうちに自然の森のような、生物である自分と向き合える場所でひとりを感じることも必要だと思うのです。親御さんが子どもたちのことを気にかけ過ぎて、なるべく世の中の危険や嫌な面を見せたくないと思って頑張れば頑張るほど、社会の実態を知らないで大人になってしまうことになるんです。「世の中には野獣がいっぱいいるのよ」ということを、隠すのではなく、子どもの時にちゃんと教えてあげなければいけない。つきっきりで側にいるのじゃなくて、「何でも経験していらっしゃい。いつでも帰ってきていいし、何かあったらお母さんが守るからね。どこにいても助けてあげるから」という姿勢は大事だと思います。私の場合母のそういう距離感がありがたかった。
三枝:なるほどね。みなさん、自然に身を置くことがすごく大切ということをおっしゃるんですけれども、それプラス、瞬間でも孤独感をちゃんと味わう。そういうことですよね。
ヤマザキ:そうです。そういう孤独を、成長の機会のひとつとして捉えられずに避けて通ってしまうと、なにかあった時に、やっぱり自分の弱さの対処に困起ってしまうような自体になるのだと思います。
私は時々、子どもの時の感覚を呼び覚ましたい欲求がわくことがあって、そんな時は近所の等々力渓谷や多摩川河川敷を一人で散歩します。樹木や川べりだと生体反応がどっからともなくあってね。虫だったり鳥だったり。そうすると「生き物は地球から守られて生きている。孤独だとかいってメソメソしているのは人間だけだ」という実感が湧く。自然の中には生きる拠り所となるようなメッセージがたくさん溢れています。自然の中に身をおくと、「生きていていいんだよ。息できるでしょう。お日様も照っているでしょう。緑もあるでしょう」って。それだけで、「ああ、そうね。私は、生きていてよかったのね」と思えるじゃないですか。
S:ヤマザキさん、現代のレイチェル・カーソンですね(笑)。『センス・オブ・ワンダー』の。

レイチェル・カーソン著『センス・オブ・ワンダー』新潮社
ヤマザキ:『センス・オブ・ワンダー』は素晴らしい本ですね。
三枝:カーソンも近いことを書いていますよね。自然は帰る場所であり、知ることよりも感じることが大切だと。森をどう感じるか。千差万別だけれど、その感性は生きるために必要だということ。生きているといろんなことがある、その時に、自分がリセットを出来る場所を持っていることが大切、ということなのかな。
ヤマザキ:そうですね。自然は、「生きていて良いんだよ、生まれてきて良かったんだよ」というメッセージをもらえる場所ですね。
うちの息子、デルスというのですけど、『デルス・ウザーラ』という黒澤明の映画からとったんです。デルス・ウザーラは、伝説上の人物なんですが、東シベリアの未開の地に大自然と共存して生きる孤独な猟師です。彼は、最終的には発達した文明の犠牲となって不条理な死を遂げてしまうのですけれど、その全編から、彼が地球に愛されて生きているということが横溢してくるんです。
息子にも、誰かから愛される以前に、デルス・ウザーラのように「地球から愛される人」になって欲しい。「生まれてきたよかったんだよ、あなたは」という地球からのメッセージを感じられる人になってもらいたいと思って名付けました。
家族と死に別れたり、もしくは家族が破綻してしまうこともあるかもしれない。でも、何はともあれ、人間関係よりも絶対的に裏切らない、完全な真実って思えるのはこの地球という惑星で他の生物ともども生きているということ。大気圏内に生まれてきた命を全うすればいい。すごくシンプルなことじゃないですか。
『ゼロ・グラビティ』っていう映画を時々思い出すんですが、あれは宇宙から無事地球に帰還できるかどうかという話です。主人公にとって、どこの国のどこに着くかなんてどうでもいいんです。大気圏内に帰ってきて息ができているっていう、その安堵をあのラストシーンを見た人は誰しも感じるんじゃないでしょうか。地球はどんな生きものにも平等に生きていける環境を提供してくれている。それだけでもう充分。
人間は社会的な生き物ですから団結できるように細かいルールを作っては理解を共有したがりますけど、うまく行かないから戦争のような軋轢が発生する。倫理観が違ったり相互理解は成立しなくても、お互いの生き方をリスペクトしながら共生していけばいいのです。人間以外の生き物は皆種族が違っても森や海の中で皆共生しています。

三枝:「地球に愛される人になれ」という言い回し、うちも使わせていただいていいでしょうか。
ヤマザキ:もちろんです。広めて欲しいくらい。
さっき三枝さんが、うちのベランダから見える畑をさして、「これ、誰の畑ですか?」って聞いたでしょう。悠々自適に畑をいじっている姿に、この辺の人たちもみんな羨望の眼差しを送っているんですよね。いいなぁって。あそこの土地は誰にも売らないで欲しいなってね。これも「自然との共生」の大切さに人々が気づき始めたということの表れですね。
三枝:僕が世田谷にあった祖父母の家に住んでいた頃は、「世田谷にはまだ田んぼや畑がある」って言われていた。むしろ早く開発してくださいみたいな感じでしたね。それが今、ちゃんと価値として、わかる人にはわかるようになったのは、進化なのかもしれないです。
ヤマザキ:高度成長期の頃の日本は戦争からの復興の焦りもありましたから、変化は仕方のないことだったと思います。
それこそサヱグサさんができた開国直後の明治2年なんていうのは、日本は早く進化しなければ列国に支配されてしまうぞ、という焦りで西洋化に拍車がかかっていた。でもそれは終わった話ではなくて、実は私たちって、まだその勢い余った西洋化の継続上にいるような気がするんです。教育や政治や建造物や衣服など一気に西洋化を図っても、中身がついていけていない。日本という独自の土壌の中で育まれてきた宗教観や人間性を考えると、西洋化にもリミットがあると思うわけです。これは、コロナ禍で、日本にずっとこんなに長くいることはなかったこの2年間で、考えさせられたことのひとつですね。
三枝:そうですよね。日本人としての誇りもあるべきだし、良いところも沢山あるはずです。
ヤマザキ:「自然との共生」というのは、まさに素晴らしい日本らしさだと思います。日本人には、八百万の神がいて、どんなところにも小さな命が宿るということを大昔から愛でてきた人種です。でも、西洋人というのはインフラの面においても、古代ローマ時代から土の上に石畳を敷き詰めて、人間が自然を支配してこれだけのことをやっているんだと、人間至上主義的な意識で覆ってしまう。地中海文明はそういう進化を遂げたけど、自然とうまく共生できている日本にはそんな歴史のある西洋のインフラ感覚は適応しないと思うのです。
三枝:おっしゃる通りですね。明治の文明開化におけるヨーロッパ風の西洋化の後に、敗戦でアメリカ化が推進され決定的にアイデンティティを失っていった。きっと日本は、まだそこに留まっているのですよね。従来型の資本主義経済が限界だと言われつつも、新たな方向性は見出せておらず、今しばらくはその中でもがいて生きていかざるを得ない。昔の日本には自然が身近にあって、大家族での暮らしや隣近所の人たちとのコミュニティもありましたが、それが今、全部分断化されてしまった。極論ではその時代に戻せばいいとう話になってしまうんですが、今の時代、そうはいかないですね。そうすると、資本主義経済の中で生きていく逞しさと、同時に戻れる場所を持つということが大切になってきますね。
ヤマザキ:フレキシビリティーですね。
三枝:そういうことをフレキシブルに出来る大人になるには、どういうことを、小さい時に体験したらいいんでしょう。
ヤマザキさんはスティーブ・ジョブズの漫画を書かれていますが、その冒頭に、文系と理系の交差点のようなことをおっしゃっていたでしょ。その言い回しをお借りするなら、子ども達には、資本主義経済と地球・自然との交差点みたいな「体験」の場を作ってあげることが出来たらいいのかもしれませんね。頭で理解するのではなくて、直感的に感じて、「自然に戻れる力」も身につけてもらいたい。

ヤマザキ:養老先生は江戸時代のような「参勤交代」をまたやればいいんだって、よく仰っていますよね。参勤交代までいかなくても、私は息子がまだ小さい頃から、それはもうよく旅行に連れて行きました。何もない南太平洋の、それこそみんな、腰蓑を巻いているだけのような場所に連れて行ってしばらく滞在していると、彼は自然に現地の子どもと仲良くなったりしていました。
世界にはあらゆる価値観が山のようにあって、文明が進化していれば良いという問題ではない。資本主義経済のなかでお金がよく回ることも、人間としての才覚による結果だけれども、それが全てだとその社会のシステムにしがみついていていれば安心というものではない。自然には、人間がなせないすごい現象がそれはそれは沢山ある。人間もそういったそれぞれの地域によって考え方や生き方も違う。価値観の多様性を子供に知ってもらいたくてあちこち連れて行くわけです。そうすると、子供も東京や日本が世界の全てじゃないということわかってくるようになる。
三枝:なるほど。そうかもしれませんね。
ヤマザキ:2015年ミラノで食をテーマにした万博があって、私はテレビの取材でそこへ行ったのですけど、会場では各国が競ってパビリオンを建てているわけです。日本もチームラボの映像を使ったりして話題になり入場待ち時間が4時間とかでした。アメリカのような先進国はすごいのを作っているわけですよ。ところが、一角だけ何にもないところがあって。「何これ?先進国ブースなのにどうしたんだろう?」って思ったら、そこは、オランダでした。パビリオンをあえて建てず、芝生だけひいて、現役のキッチンカーをオランダから連れてきただけ。観客はみんな、オーガニックでエコなご飯を食べて、ビール飲んで、気持ちよさそうに芝生に寝そべっている。「ああー。この国の人たち頭いい。着眼点が一歩先にあるんだな」と思いましたね。
三枝:ああー。そうだったんですね!オランダのブースが最もシンプルなのに一番メッセージ性が高かったのでは?
ヤマザキ:立派な建造物やテクノロジーをどれだけ駆使しているかどうかが、資本社会や文明の尺度ではないとしっかり考えている点に感心しました。日本も本当は、こういうことを出来る国なんじゃないかなって思うんですよね。
三枝:先日開催されたオリンピック・パラリンピックも日本にとってチャンスだったのかもしれないですよね。
ヤマザキ:そうなんですよ。『オリンピア・キュクロス』っていう漫画でも描いていますが、例えば、「昔の代々木の競技場を綺麗にして、過去へのリスペクトを込めて、もう一度使います」なんてことをやったらかっこよかったのになあ、なんて思うわけです。
日本は「侘び寂び」という美意識がある国であることを世界は認識している。だったら古いものを長く使いますという姿勢を示していたとしたら、世界中がいい意味でびっくりしましたよね。お金を使うよりも素敵な見せ方があったのにね。そうしたら、コロナ禍になって滞留したって、ダメージも負担も少なかったのではと思います。
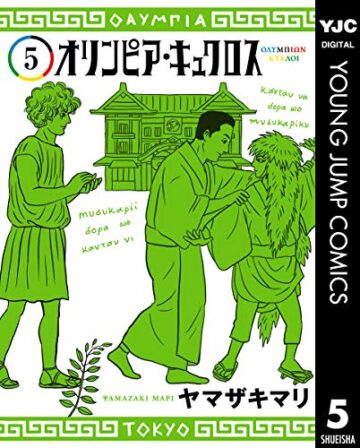
『オリンピア・キュクロス』集英社
三枝:結局、今回のオリンピック・パラリンピックでは選手たちの活躍に大いに感動しましたが、日本という国としてのメッセージ性は中途半端になってしまい、それがすごく残念でした。ヤマザキさんのおっしゃっている日本独自の美意識は、コロナ禍だからこそ世界に発信して欲しかったと思います。
私は、日本が本当の幸せな国になるための一番の近道は、子どもたちの善き成長だと思っています。サヱグサにも、お手伝い出来ることがあるんじゃないかと思って、準備を進めているわけです。ですが、弊社がこれまで、銀座という街、子ども服という商売を通して見ていた世界だけですと偏ってしまいますので、ヤマザキさんや養老先生はじめこの対談でご一緒した方々などに見知をご教授いただきたいと思っています。いわゆる一方的に詰め込む「教育」にはしたくないんです。受験に有利ですというのとも違う…

ヤマザキ:すごく大事なことですね。いわゆる教育現場以外での体験が、本当に大切な「教育」だったりします。
私の母親の育て方の例で言えば、彼女は音楽家だったので、今日は素晴らしい楽曲の演奏があるというときは私たち姉妹に学校を休ませるんですよ。「今日は学校行かなくていい、うちのオーケストラに来なさい。素晴らしいから」と。我が家には頻繁に休んでいいがあったわけですよ。お天気が良くて、母もたまたま練習もリハーサルもなにもない日。そうすると「もう、こんなに一緒にいられる日はないから、今日は休もう」と言って、親子三人で車に乗って遠出して、山登りをしたりとか。
三枝:なるほど。素晴らしいお母様ですね。
ヤマザキ:謂わゆる世間体に対してのプレッシャーが彼女には無くて。「どうやったら、この子達は強く逞しく明るく生きていけるか」ということはいつも考えているけれど、でもそれは、世間のいう教科書からは学んでいないんですよね。学校が全てを教育してくれるわけではないという確信があるわけです。
それは、母が戦争体験者だったり、東京から北海道に移り住んだ勇気を持っていたというような、いろんなコンテンツからくるものだと思うけれど、でもやっぱり、「真の教育」というのは何かと考えた時に、一般化されたスタイルが全てではないという信条があったのだと思うんです。
三枝:そうですよね。いまの子どもたちは、いい点数をとるとか、いい学校に入るとかのために、非常に忙しいわけですね。ですから私は、そういう本質的な大切さを伝えたいと思っているのですけれど。お子さんによって気づき方も感じ方もそれぞれ違いますから、それぞれがささやかでも何かを感じてくれれば良しとするような場所作り、人との出会いをお子さんたちに提供できればいいなと思っています。
ヤマザキ:とてもいいと思います。子どもたちも、世間的な評価でしか自分の人生の質感を実感できなくなってしまっている。いい学校、それはそれであるけれど、それとは別のとこからも自分の為にもなり、楽しいことからだって学べるんだ、ということを提供されるのは素晴らしいです。
三枝:ヤマザキさん、ぜひ、うちの講師としてやっていただけませんか。

ヤマザキ:はい、私でお役に立てるのであれば(笑)。数年前、NHKの「ようこそ先輩」という番組で、北海道時代に通っていた母校に行ったんですけどね。「漫画家だからといって漫画を教えるのは嫌。昆虫を採りにいく授業がしたい」と提案したんです。大自然のど真ん中の学校だから、みんな昆虫なんて平気でさわれるのかと思ったら、二人、三人といないんですよ。さわれる子が。北海道なのに。
三枝:え〜北海道なのに(笑)。
ヤマザキ:「そんな!まわりみんな山じゃない?土もあるじゃない?」って言ったら、子どもたちは「虫は考えていることがわかないから怖い」と。
「考えていることがわからないから面白いんでしょう!」って、最初から説教モードになってしまって。「わ〜、怖いおばさん来た〜」みたいな感じになっちゃったんですけど(笑)
三枝:あはは、説教モードかー(笑)。
ヤマザキ:テレビに映るとことを意識しての上でのことだと思うのだけど、クラスのリーダー格の女の子なんかは、ひらひらのついたノースリーブにショートパンツ姿だったんですよ。「あなた、これから虫採りに行くのよ?」って言ったんですけど、案の定、「あ〜ん、刺された〜」って大騒ぎ。私は知らんぷりしてました(笑)。
三枝:北海道でもそんなことになっちゃったんですね(笑)。
ヤマザキ:撮影の1日目に山に入ったんですけど、夢中になってしまって、はっと気づいたら周りに男の子三人しかいなくて、彼らが「先生、みんな置いてきちゃったんですけど、いいんですか?」って不安そうにしてて。遠くから「ヤマザキさーん、どこですかー!?」ってTVのクルーの声が聞こえて(笑)。
その三人の男の子たちがね、「やっと、昆虫が好きだってことが言えた」っていう開放感があったみたいで、次の日、実は飼っているって言って虫かごを持ってきたんですけど…
三枝:かわいい。
ヤマザキ:でも、籠の中に入っていたのはカマドウマっていう、俗にいう「便所コオロギ」(笑)。「先生、これ、名前わからないけど、すごい虫かもしれない」って言うから「ううん。これはね、便所コオロギっていうんだよ」って教えてあげましたけど(笑)。ミミズを持ってきてくれた子もいましたが、彼らはそれまで、自分の好きなものをみんなで共有することが出来てなかったんですね。可哀想なことに。
課題は虫捕りだけじゃないんです。「みなさんが散々嫌いだって言っている虫なんだけど、じゃあね、あなたたちが明日の朝、起きた時に虫になっていたらどうする?」って。カフカの「変身の」応用ですね。「あなたはハエが嫌いだと言ったけれど、もしあなたがハエになっちゃったらどうする?客観的な立場から考えてみて」と、作文を書かせたんです。クラスでも優秀でちょっとハンサムな男の子2人は、カブトムシ、クワガタ。リーダー格の女の子はひらひらの蝶々でした。やっぱりという感じですね。その子にいつもくっついているお付きみたいな立場の女の子は、すごく可愛い子だったんですけれどね、蛾を選択していたんです。露呈するんですね。漫画が得意な男の子が一人いたんですが、その子が変身する虫として選んだのはミミズでした。
三枝:ミミズですかあ。
ヤマザキ:「ミミズは、土に籠ってずっと漫画を描いている」っていう設定だったかな。ところが、そのミミズがある日学校帰りの少年に見つかる、つまり自分に見つかるんです。「あ、しまった、踏まれる!」とミミズは思うんだけど、少年はしゃがんで、じいっとミミズを観察して、土を上からかけてくれた。っていう話なんです。おおって思って。この子はきっと家庭環境が温かいのかなって思いました。あとは、気象予報士の子がトンボだったかな。日記みたいに「○月○日天候晴れ」って天候がいちいち書いてあって、お父さんの仕事をよく洞察しているんだなっていうのが見えてきた。あと、カタツムリだった子もいましたね、いつも遅くてみんなに怒られるけど、でも、カタツムリを見ると安心するって書いていたんです。虫に置き換えた時に自分が客観的に見えてくる。言えずにいた心の中の声も吐露されていた。
三枝:ミミズが好きだとか、言えずにいたということですか?
好きなものが好きって言える場づくりが大事ですね。何かを通してね。

ヤマザキ:言いたいことをちゃんと言語化するってとても大切です。
今回のコロナ禍で一番興味深く思ったのが、世界全体が同じ問題に向き合った時に、各国の首脳レベルの人たちの、弁証法とか、弁論というのを子どもの頃から、当たり前に身につけた人とそうでない人の差異がはっきり出てしまったところですね。
三枝:それは、伝える力ということですか?
ヤマザキ:はい。メルケル首相が演説で、二人称で呼びかけているのを見たときは、さすが弁証教育の国の首相だなあ、と感心しました。「そこに座っているあなた、スーパーで棚卸しをしてくださっているあなた、本当に感謝します。」って。みんな、ああいう言葉を欲していた。激励されたかったんですよね。
ところがね、日本の偉い人たちは、言語化して、インパクトのある言葉を言論するってことに、まだ、馴染んでいないので、どうしても紙に書いてあることを読みあげるだけになってしまう。
三枝:そうですね。誠意も感じなかったですし、少なくとも心には響いてこなかった。
ヤマザキ:日本は中途半端に西洋化してしまっていますから、そこは曖昧にしておいてはいけないところだと思うんです。全てを言語化しなくても阿吽で理解するという日本式の美徳は素晴らしいけれど、西洋風の構造となっている政治の場では通用しないですからね。
なので、しっかり場を認識してどういった手法を取るべきか判断のできる教育というものが、これから学校のプログラムとして必要になってくるんじゃないかと思うのです。
例えば試験も紙に答えを書くばかりではない口頭試問とか、小さなことからでいいですよ。「あなたの読んできた本、何が良かったのかみんなの前でしゃべってみてください」とか、「歴史の勉強をしましたけど、あなたの覚えてきたことをみんなに教えてください」とか。子どもに先生役をさせるのは、理解が深まりますし、とてもいい方法です。イタリアでは小さいうちからこの訓練をします。

三枝:なるほど、そうなんですね!
ヤマザキ:私は17歳からイタリアの学校に入ったのですけれど、それまでの日本の高校の教育方向性と全然違いました。はっきり自分の考えを言語化出来ない人は潰されてしまう。だから、日本にいると「ヤマザキさんたら、人のしゃべっているところに、どんどんかぶってきますね」と呆れられますけど、それはイタリアへ行った頃からそうせざるをえなかったという。弁解するようですけれど(笑)。
三枝:いやいや、なるほど。日本人は、考えを伝えて人の気持ちを動かすということに対しての努力が足りないのかもしれませんね。
ヤマザキ:はっきりモノを言ってしまって地雷を踏む、なんてことがないように気を配っていることが、元気のない日本、魅力のない日本につながってしまっている気がしますね。
三枝さんはバブルの時の日本をバリバリご存知でしょうけど(笑)、1980年後半とか90年代初頭は、若者がみんな怖いモノ知らずで大胆でした。いいとこの坊ちゃんたちも、リュックひとつ背負って「ちょっと海外行ってくるわ」って。バックパッカーが流行りましたよね。街ではみんな肩パットで、自分の何倍も大きく見せて、何倍もかっこつけた恋愛してね。男も女もね。彼らには失敗や恥ずかしさと向き合える勇気があった。ひとりひとりが生きることを謳歌していたあの時代を時々懐かしく思うことがありますね。ところが今は「自分いません。あんまり自分に気づかないでください」って感じの子が多いですよね。
三枝:先日対談した野口健さんも同じようなことをおっしゃていました。一括りにしてはいけなけれども、近頃は、冒険どころか何にも興味を持てない感じの子も多いですよね。そうなるとやはり、一方的に教えるつもりはないんですけれど、子ども達の本来の興味が引き出せるような場づくりとか、状況を作ってあげるっていうのが大切なのかなって、改めて感じました。
ヤマザキ:そういうのは半ば強制でもいいと思うんです。イタリアの子どもを見ていると、みんな小さい時から美術館などに強引に連れて行かれます。日本だと、つまらないと愚図られたら困るからと連れていかない親が多いみたいですが、イタリアはそんなのおかまいなし。
「こういう素晴らしいモノが、私たちの生活に密接しているんだ」ということを、幼い時から当たり前のように伝えようという考え方があります。それこそが本当の教育ですよね。
それから、先ほどの昆虫の作文もそうですが、子どもには、苦手なことも客観的に見て、なぜ苦手なのかを自分で分析するというような機会をもっと持たせるといいと思います。嫌いな人がいる、なぜその人が嫌いなのか。いじめたい人がいる、では、なぜいじめたいのか。さらに、もし、自分がいじめられる方の立場になったらどうなるかを作文に書いてみる。つまり大切なのは想像力なんです。想像力が欠落していくと、客観性が持てなくなってしまいます。
三枝:そうなると、人間関係がどんどん変わっていってしまいますね。リアルでは他人のことが理解・共感出来ないのだけど、自分の意見をちょっとSNSに出せば、共感者がその世界には必ずいるから、それでほっとして終わるという。
ヤマザキ:そうです。ものすごい怠惰な対処法ですよね。自分で言語化しなくて済むんですよ。例えば、私がTVやツイッターなどで何か発言したり書いたりすると「ヤマザキさんが私の思っていたことを全部言ってくれた。嬉しい」って反応していたりするけど、それではいけないと思うんです。自分で言語化できない考えなんて質感もなく消えてってしまいますから。でも今は多くの人が他人の言葉にぶら下がっちゃって、知ったつもり発言したつもりになってしまう。

『ヴィオラ母さん』文藝春秋
三枝:ヤマザキさんの『ヴィオラ母さん』では、親子の距離感について色々考えさせられました。
ヤマザキ:数年前から新聞の人生相談欄の回答者を受けていますけど、最近、「親だったら普通これこれなのに、こんなこともしてくれない。マリさんどう思いますか?」っていうような相談が多いんです。それに対する私の答えは、親という定型に当てはめようと思うからそういう気もちになるのではないか、というものでした。
この世にはいろんな親がいて、血が繋がってはいても、性格も考え方も千差万別なのだと思うようにしたら、親が突飛な行動を起こしても、ああ、こういう人もいるんだなで済むことなんです。
子育ても同じで、無骨であろうとなんであろうと、余計な思惑を盛り込まずに見返りを求めない素直な愛情を持っていれば、どんな反抗期を迎えていても、「親は自分を愛してくれている」ってことは伝わるし、必ずどこかで感謝の形として出ると思うんです。
三枝:そうですよね、なんだか安心しました。私も娘が22歳で…。この前、彼女の部活の試合を競技場まで足を運んで応援に行ったのですが、その場ではものすごくそっけなかったのに、後日、親が笑顔で応援してたことが嬉しかったとSNSに挙げていて(笑)。言わなくていいからせめて表情に出してほしいなとは思いましたけれど、感激しました。そんな感じで十分なんですよね。
ヤマザキ:その奥ゆかしさが素晴らしいじゃないですか。こういう場合は、言わないからいいってこともあるんですよ。
三枝:思えば自分だって、親に何かしてもらった時だって、そんなこといちいち表現してませんでしたものね。
ヤマザキ:私の母は89歳なのですが、昭和一桁の人だから、愛情表現なんてひとつも出来ないし、むしろ卑下するくらい。「うちの娘は全然だめ。下手くそな絵しか描かないし」とかって人前で言うくせに、家で私が絵を描いているのをみると「いいなあ、絵が描けて」って(笑)。そういうのを人前で言おうよって。でも、ああ、こういう人なんだな、見栄っ張りなんだなって、ただ思えばいいんです。
母とは手を繋いだことも、ハグしたこともないです。するとイタリアの姑が、「あなたたち母娘は気が狂っている!そんなに長い間、会っていなかったのに、ハグもキスもしないなんて!」って。母の感触なんて感じたこともないって言ったら「信じられない!」って驚くわけですよ(笑)。「あなたたちの価値観では信じられないかもしれないけど、そういうのは日本だと依存に走っているみたいに取られることもあるから、一緒にしないで」って言ったら、わけがわからないっていう顔をしていました(笑)。そういうことなんですよね。家族の距離感にだって多様な捉え方があるんです。
三枝:(笑)、勇気が出ました。娘は何も期待していないでしょうけど、こちらも期待しないように、でいいんですよね。
ヤマザキ:いいんですよ。そのくらいの距離感で。ふとしたときに感謝っていう感じでね。

三枝:『ムスコ物語』を拝読して、デルスさんとマリさんの関係も本当に素敵だなと思いました。いまはどうされているんですか?
ヤマザキ:息子はコロナ前にラオス、ネパールを旅していましたが、出家したお坊さんみたいになって帰って来て(笑)。この間フードデリバリーでオムライスを二つ頼んだのに一つしかこなかったんです。「お金も振り込んでいるのにおかしいじゃない!」と息子に電話をかけさせたんですけど、すごく穏やかに相手と話している。私が後ろで「怒れ、怒れ」って言っても、「はい。わかりました。よろしくお願いします」って穏やかに切っちゃった。どうして、怒らないの?こういう時ははっきり言わなきゃだめなのよ!?っていう私に、「でもね、母、こういう時ね、気分を害している人があなた一人か、それとも、僕と、電話のむこうの人、配達してくれた人にまで増やすのとどちらがいいですか?」と坊さんの説教みたいな返事が返ってきました(笑)。「そこで怒ってみんなで嫌な気分になったところで何のメリットもないでしょう?」って。「はい。確かにそうですね」ってなりました(笑)。
「怒ったって何の解決にもなりませんから。いま持ってくるって言ってましたから、母、先に食べててください」って。
三枝:どっちが親かわからない(笑)。
ヤマザキ:それで、まもなくして届いたら、オムライスが2個入っていた。息子がドヤ顔で「ほら。2つ。こういうことなんだよ、母。わかった?」って(笑)。
三枝:いや〜(笑)、その年齢で素晴らしいです。でも世の中、そういうことで上手くいくことって本当にある。争いを避けたいわけじゃなくて、善きにまわっていくっていう発想になれる人ってすごいですよ。
ヤマザキ:ほんと、すごい。うちの息子って怒ったことがないんですよ。心配になって「怒ったほうがいいんじゃないの、それはメンタル的にやばいよ」と言ったら、「いや、怒る必然性がないのに怒ってもしょうがない」って。諦観というか、あらゆる国であらゆる体験をしてきちゃっているので、腹がすわっているんですよね。私の方がむしろ知らないですもん。現地の学校に入り続けてきたわけじゃないから。
三枝:それこそ、多様性を認める力が身についているんですね。
ヤマザキ:そうです。あの人はどこに行ってもびっくりするくらい動じない。だから、ネパールだのラオスだのに行っても、なんてことなく帰ってくるんですね。
三枝:かっこいいですねー。
ヤマザキ:これからどうするんだか。とりあえず日本で働いてみて、先のことはゆっくり決めるみたいなこと言ってました。私だって42歳になって漫画がヒットするまでは、どうなるかわからない人生を過ごしていたわけだから。なんでもいいから色々やっていれば、どこかで必ず結果が出るんでしょうから。
三枝:早咲きの人もいるし、遅咲きの人もいる。そこを、一律に考えてしまいがちですけど、何歳のときにはどうなっていないといけない、みたいな押し付けはくだらないのかもしれないですね。
ヤマザキ:本当にくだらない。長い人生を振り返った時、そんなのは、はっきりいって何の意味もなさないことになっていきますから。
三枝:それより、何を経験したかですよね。今日はヤマザキさんのお話を伺って、僕も生きる力が沸きました。明治から続いていた小売業からの転進はそれなりの勇気が要ることですが、これも僕にとっては人生の貴重な体験の1つです。これから五代目としてどうして行くか、しっかりと、長い目線を持って向き合っていきたいと思います。
ヤマザキ:それはもう、マニュアルなしでどんどん行かれればいいと思います。子どもたちに体験を提供する事業というのは、とてもいいと思いますから。
三枝:ご一緒できることがあれば、ぜひまたよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。

◎ヤマザキマリさん 書籍のご紹介
『ムスコ物語』幻冬社
国籍?いじめ?血の繋がり?受験?将来?
は?なんだそりゃ。
「生きる自由を謳歌せよ!」『ヴィオラ母さん』で規格外の母親の一代記を書いた著者が、母になり、海外を渡り歩きながら息子と暮らした日々を描くヤマザキマリ流子育て放浪記。(幻冬社HPより)
いまSAYEGUSA は、子どもたちが様々な感動や気づきに出会える環境を創造するブランドとして生まれ変わろうとしています。 SAYEGUSA が提供するホンモノの体験を通じて 子どもたちの感性や創造力を、もっと大きく、もっと力強く育ててあげたい。彼らの無限の可能性を引き出し、その未来をかたちづくるホンモノの体験を丁寧にひとつひとつ差し出せるような 夢いっぱいの”ワンダーランド(プラットフォーム)”を目指したいと考えています。 新しいSAYEGUSAをお披露目するまでの間、対談コンテンツ「Sayegusa Experience Talk」を配信いたします。大空に飛び立つ綿毛を見守るタンポポのように三枝亮とゲストが、夢に向かって飛び立っていく子どもたちにエールを送ります。
- 関連記事









